経営戦略の思考法
時間展開・相互作用・ダイナミクス

経営戦略の思考法
著者:沼上 幹
出版社:日本経済新聞出版社
出版日:2009/9/26

内容
リソースベース、ポジショニング等々様々な考え方が入り乱れている経営戦略。経営学の第一人者が切れ味鮮やかに戦略の地図を解説し、組織の暴走、シナジーの崩壊などの問題点も浮き彫りにする待望の経営戦略入門。 経営戦略に関する5つの考え方、戦略計画学派、創発戦略学派、ポジショニング・ビュー、リソース・ベースト・ビュー、ゲーム論的アプローチのそれぞれを体系的にわかりやすく整理してくれている。
目次
|
|---|
| 第Ⅰ部 | 戦略思考の変遷―経営戦略論の知層経営 |
|---|
| 第1章 | 経営戦略に関する5つの考え方 |
|---|
| 第2章 | 戦略計画学派 |
|---|
| (1) | 戦略計画学派の特徴 |
|---|
| (2) | 用語の整理とオリジナル概念の提示 |
|---|
| (3) | 戦略策定手順の提示 |
|---|
| (4) | まとめ |
|---|
| 第3章 | 創発戦略学派 |
|---|
| (1) | 創発戦略学派の基本的な特徴 |
|---|
| (2) | 近年の実態 |
|---|
| (3) | まとめ |
|---|
| 第4章 | ポジショニング・ビュー |
|---|
| (1) | ポジショニング・ビューとは |
|---|
| (2) | ポジショニング・ビューの具体例 |
|---|
| (3) | GE社のプロジェクトに関する注意点 |
|---|
| (4) | ポジショニング・ビューのまとめ―貢献と問題点 |
|---|
| 第5章 | リソース・ベースト・ビュー |
|---|
| (1) | リソースあるいはコンピタンスへの注目 |
|---|
| (2) | 経営資源の探求 |
|---|
| (3) | リソース・ベースト・ビューとポジショニング・ビュー |
|---|
| (4) | リソース・ベースト・ビューのまとめ |
|---|
| 第6章 | ゲーム論的アプローチ |
|---|
| (1) | ゲーム論的アプローチの台頭 |
|---|
| (2) | 競争と協調の混在 |
|---|
| (3) | 競争と付加価値 |
|---|
| (4) | 取引条件の分析 |
|---|
| (5) | まとめ |
|---|
| 第7章 | 5つの戦略観がもたらす反省 |
|---|
| (1) | 5つの戦略観の位置づけ |
|---|
| (2) | 5(6)つの戦略観という複眼 |
|---|
| (3) | 知的地層の形成 |
|---|
| (4) | 戦略計画学派に見る知層形成 |
|---|
| (5) | 日米の戦略バイアス |
|---|
| (6) | その他の戦略バイアス |
|---|
| (7) | まとめ |
|---|
| 第Ⅱ部 | 戦略思考の解剖―メカニズムの解明 |
|---|
| 第8章 | 3つの思考法 |
|---|
| (1) | はじめに |
|---|
| (2) | カテゴリー適用法あるいは思考の欠如 |
|---|
| (3) | 要因列挙法とメカニズム解明法 |
|---|
| (4) | 要因列挙法とメカニズム解明法 再論 |
|---|
| (5) | メカニズム解明法へのステップ |
|---|
| (6) | 人間的な行為と相互作用 |
|---|
| (7) | おわりに―3つの思考法と戦略観の分類図式 |
|---|
| 第9章 | 戦略的思考法の具体例―思考法を身につけるための見本例の紹介 |
|---|
| (1) | はじめに |
|---|
| (2) | そもそも戦略とは何であろうか |
|---|
| (3) | 伊丹敬之『経営戦略の論理』―空間→時間→相互作用 |
|---|
| (4) | 小倉昌男『小倉昌男 経営学』― 一に典型、二に集計 |
|---|
| (5) | 葛西敬之『未完の「国鉄改革」‐巨大組織の崩壊と再生』―人間くささを盛り込む |
|---|
|
| 第Ⅲ部 | 戦略思考の実践 |
|---|
| 第10章 | 顧客ダイナミクス |
|---|
| (1) | 同一個人の変化という視点 |
|---|
| (2) | 加齢による変化 |
|---|
| (3) | 顧客の学習 |
|---|
| (4) | 顧客が「学習してしまう」ことで市場が読みにくくなる |
|---|
| (5) | ネガティブな学習 |
|---|
| 第11章 | 顧客の声に耳を傾けてはいけないとき |
|---|
| (1) | 誰の声を聞けばよいのか |
|---|
| (2) | 『イノベーションのジレンマ』 |
|---|
| (3) | 営業と技術の悪循環 |
|---|
| (4) | 顧客に搾取される危険 |
|---|
| 第12章 | 差別化競争の組織的基礎 |
|---|
| (1) | 「差別化せよ」という競争戦略の要諦 |
|---|
| (2) | チャレンジャーの定石に対する疑問 |
|---|
| (3) | リーダーの組織 |
|---|
| (4) | おわりに |
|---|
| 第13章 | 競争を活用する戦略 |
|---|
| (1) | はじめに |
|---|
| (2) | 競争回避―1980年代後半のモスフードサービス |
|---|
| (3) | ライバルの効用 |
|---|
| (4) | 他社の競争を利用する |
|---|
| (5) | おわりに |
|---|
| 第14章 | 先手の連鎖シナリオ |
|---|
| (1) | 先手必勝は有効な指針か |
|---|
| (2) | ネットワーク外部性 |
|---|
| (3) | 製品価値の捉え方再考 |
|---|
| (4) | ネットワーク外部性の低い場合の先手 |
|---|
| (5) | おわりに―ネットワーク外部性とチャレンジャーの「差別化」 |
|---|
| 第15章 | シナジーの崩壊メカニズム |
|---|
| (1) | シナジーのコスト |
|---|
| (2) | デバイス内製の罠 |
|---|
| (3) | おわりに |
|---|
| 第16章 | 選択と集中―創発的多角化戦略の問題点 |
|---|
| (1) | はじめに |
|---|
| (2) | 多様性への愛 |
|---|
| (3) | 「集中せよ」の原則と矛盾する多様性重視 |
|---|
| (4) | 平時の多様性と戦時の集中は両立可能か |
|---|
| 第17章 | 組織暴走の理論 |
|---|
| (1) | はじめに |
|---|
| (2) | 組織の要因 |
|---|
| (3) | 心理的な要因 |
|---|
| (4) | 競争相手との相互作用 |
|---|
| (5) | 《英断》と《暴走》の判断の難しさ |
|---|
| (6) | おわりに |
|---|
| エピローグ | 経験知と反省的学習 |
|---|
| (1) | 人は実践から学ぶ |
|---|
| (2) | 苦労の過剰正当化 |
|---|
| (3) | 安定的なコミュニティ―内の知 |
|---|
| (4) | 反省的対話 |
|---|
| 参考文献 |
|---|
| 人名索引 |
|---|
| 事項索引 |
|---|
|
Training Information
おすすめ企業研修




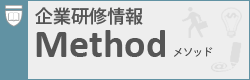
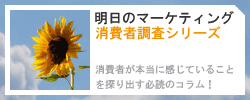
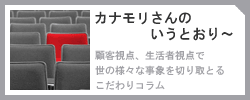
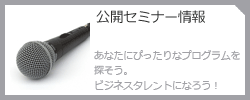
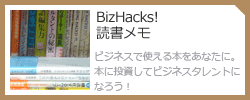
![[読書メモ]世界を制した20のメディア [読書メモ]世界を制した20のメディア](/images/banner/09040301.gif)
![[読書メモ]スパークする思考 [読書メモ]スパークする思考](/images/banner/09040801.gif)