TOP » 読書メモ » ラーニング・リーダーシップ入門
ラーニング・リーダーシップ入門
ダイバーシティで人と組織を伸ばす

ラーニング・リーダーシップ入門
著者:牛尾 奈緒美/石川 公彦/志村 光太郎
出版社:日本経済新聞出版社
出版日:2011/9/13

Amazon商品の説明より
「ラーニング・リーダーシップ入門」― ダイバーシティで人と組織を伸ばす
働きやすい職場と高業績を同時達成するダイバーシティ先進企業。多様化時代の人間力と魅力に溢れるニューリーダー像を提示。社員の個性を発揮させ、双方向コミュニケーションで組織を活性化、人材育成を実現する新手法。
目次
| プロローグ――大きく変わるリーダー像 |
|---|
| 1 | 経営環境、働き手の価値観の多様化 |
|---|
| 2 | 働きやすい職場と好業績の同時達成を目指す |
|---|
| 3 | 先進企業に共通にみられるリーダーシップ |
|---|
| 第1章 | 快活で伸びる職場のリーダーシップ |
|---|
| 1 | あなたの部下、あなたの上司の理想と現実 |
|---|
| ■ | あなたがリーダーなら、こう、お尋ねします |
|---|
| 「あなたは理想的なリーダーですか?」 |
|---|
| ■ | あなたがフォロワーなら、こう、お尋ねします |
|---|
| 「あなたのリーダーは理想的ですか?」 |
|---|
| ■ | ゆるやかさと集中のバランス |
|---|
| 2 | ダイバーシティとリーダーシップ |
|---|
| 双方向性と人材育成、組織学習 |
|---|
| もうちょっと詳しく① ダイバーシティ・マネジメントとラーニング・リーダーシップ |
|---|
| もうちょっと詳しく② サーバント・リーダーシップとラーニング・リーダーシップ |
|---|
| 第2章 | 双方向に働くリーダーシップ |
|---|
| 1 | トップ層におけるリーダーシップの双方向性――アクセンチュアの多様性 |
|---|
| 2 | ボトム層を含めた双方向性――階層にこだわらないトーク・ストレート文化 |
|---|
| 3 | 中小ベンチャー、クララオンラインの先進性 |
|---|
| 4 | 双方向性をもたせる工夫 |
|---|
| ■ | 階層の簡素化、自由闊達な企業文化 |
|---|
| ■ | 階層のフラット化+ダイバーシティ=スピードアップ――サンヨー食品 |
|---|
| 第3章 | ダイバーシティの視点から環境変化に対応 |
|---|
| 1 | 成功体験におぼれないために――IBMのダイバーシティ戦略展開 |
|---|
| 2 | 外からの視点を改革に活かす――小原琢哉氏の3つの論点 |
|---|
| 3 | 「組織学習」とリーダー――ダイバーシティを前提とする |
|---|
| もうちょっと詳しく③ 「ナレッジ・マネジメント」とリーダーシップの関係 |
|---|
| もうちょっと詳しく④ リーダー・組織・情報の関係 |
|---|
| 第4章 | 多様な個を活かすリーダーシップ |
|---|
| 1 | 多様な人材・個性を活かすために――富士ゼロックスの取り組み |
|---|
| ■ | 「強く、やさしく、おもしろく」 |
|---|
| ■ | 一人ひとりを大切に |
|---|
| 2 | すべての人を大切にする――雇用形態にかかわらず |
|---|
| 3 | 職場の「はねっかえり」が革新の種に――タレント集団でともに闘う |
|---|
| 4 | 「違い」よりも「共通点」に着目する |
|---|
| もうちょっと詳しく⑤ 個性を重視する一つの形――アクセンチュアのプラットフォーム型組織 |
|---|
| もうちょっと詳しく⑥ 「集団思考(集団浅慮)」を防止する多様性 |
|---|
| 第5章 | 組織を活性化するインタラクティブ・コミュニケーション |
|---|
| 1 | 一方通行のコミュニケーションでは多様性は活かせない |
|---|
| ■ | コミュニケーションの現状――根源的な問題 |
|---|
| ■ | コミュニケーションへの期待――現状とのギャップ |
|---|
| 2 | インタラクティブ・コミュニケーションの前提 |
|---|
| ■ | インタラクティブ・コミュニケーションとは何か |
|---|
| ■ | ダイバーシティとリーダーのコミュニケーション能力 |
|---|
| ■ | 管理主義からの脱却――スピードを心がける |
|---|
| 3 | インタラクティブ・コミュニケーションの実践 |
|---|
| ■ | 職場のインタラクティブ・コミュニケーション――上司と部下の上下が逆転? |
|---|
| ■ | 会議でもインタラクティブ――率直なやり取りを通じて、新たな人材発掘 |
|---|
| ■ | コミュニティでコミュニケーション――仕事を離れよう |
|---|
| ■ | ITの活用――素顔を知ろう |
|---|
| 第6章 | 人を育てるインタラクティブ・ラーニング |
|---|
| 1 | OJTにラーニング・リーダーを投入 |
|---|
| ■ | OJTの真髄――創意工夫と学び合い |
|---|
| ■ | 一方通行の人材育成ではダイバーシティは活かせない |
|---|
| ■ | 教え学ぶOJT |
|---|
| ■ | 多様性を認める柔軟なOJT |
|---|
| 2 | コーチングとメンタリングにラーニング・リーダーを投入 |
|---|
| ■ | コーチングとメンタリング |
|---|
| ■ | 人材育成シーンを学び合いの場として |
|---|
| ■ | 自立・自律したフォロワー育成 |
|---|
| もうちょっと詳しく⑦ 職場学習の科学――双方向性の現状 |
|---|
| もうちょっと詳しく⑧ 学習するプロセス――PDCAサイクルをベースに |
|---|
| 第7章 | 相乗効果を生むフォロワーシップ |
|---|
| 1 | ラーニング・リーダーシップ下のフォロワー |
|---|
| ■ | 時として部下が職場をリードする |
|---|
| ■ | 多様性と部下の自己実現 |
|---|
| 2 | フォロワーの自立・自律化 |
|---|
| ■ | 自己責任論を超える |
|---|
| ■ | 圧迫的な「空気」を取り除く |
|---|
| 3 | 日本的経営の再評価――PDCAサイクルの日本的な回し方に着目して |
|---|
| ■ | 日本的なPDCAサイクル |
|---|
| ■ | STPDという手法 |
|---|
| ■ | ラーニング・リーダーシップのPDCA――フォロワーの視点から① |
|---|
| ■ | ラーニング・リーダーシップのPDCA――フォロワーの視点から② |
|---|
| 4 | フォロワーを次代のリーダーへ――ラーニング・リーダーの形成プロセス |
|---|
| 第8章 | ラーニング・リーダーシップのフレームワーク |
|---|
| 1 | ラーニング・リーダーシップの全体像 |
|---|
| ■ | ラーニング・リーダーシップのスタンス |
|---|
| ■ | ラーニング・リーダーシップと双方向性 |
|---|
| ■ | ラーニング・リーダーと双方向性 |
|---|
| ■ | ラーニング・リーダーシップと多様性 |
|---|
| 2 | 自立・自律性、多様性と双方向性を育むパワー |
|---|
| ■ | コッターの議論をふまえて |
|---|
| ■ | パワーと責任のあり方 |
|---|
| 3 | ラーニング・リーダーシップの導入 |
|---|
| エピローグ――自分だけのリーダーシップ・スタイルを |
|---|
| 1 | 変化を恐れず |
|---|
| 2 | 自分自身を知るということ |
|---|
| 3 | ラーニング・リーダーシップをベースに |
|---|
| |
|---|
| あとがき |
|---|
|
Training Information
おすすめ企業研修




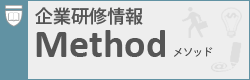
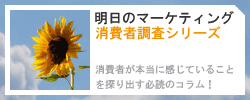
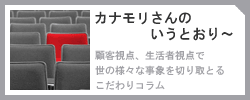
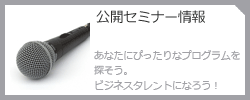
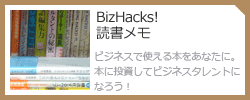
![[読書メモ]世界を制した20のメディア [読書メモ]世界を制した20のメディア](/images/banner/09040301.gif)
![[読書メモ]スパークする思考 [読書メモ]スパークする思考](/images/banner/09040801.gif)