IT社会の経済学
バークレー流入門講座101

IT社会の経済学
著者:青木 理音
出版社:インプレスジャパン
出版日:2011/9/16

Amazon商品の説明より
『IT社会の経済学』バークレー流入門講座101
■推奨文(書籍オビより)
【玉井克哉(東京大学 先端科学技術研究センター 教授)】
ツイッターではつぶやくな! グーグルには市場支配力がある!
ニュース配信は儲からない!
一見非常識な結論の、鮮やかな説明。
経済が専門でない人に、広く勧めたい。
【安藤至大(日本大学大学院 総合科学研究科 准教授)】
多彩な素材を、経済学で調剤してみせる著者の手腕が素晴らしい。
経済学なんて所詮は机上の空論、と思っている人にこそ是非読んで欲しい。
目次
| はじめに |
|---|
| 第一章 | IT企業の動向 |
|---|
| 1-1 | 企業を立ち上げるということ |
|---|
| 1-2 | サイドプロジェクトという考え方 |
|---|
| 1-3 | ユーザー評価システムの実態 |
|---|
| 1-4 | 人間関係を使った新しい検索技術 |
|---|
| 1-5 | DVDレンタルとストリーミングの関係 |
|---|
| 1-6 | サーチエンジンに中立性はいらない |
|---|
| 1-7 | プロバイダの料金体系に関する考察 |
|---|
| 1-8 | ネットのルールなんてない |
|---|
| 1-9 | オープンソースは裏切れない |
|---|
| 1-10 | グーグルのプラットフォーム戦略 |
|---|
| 1-11 | グーグルの市場支配力 |
|---|
| 1-12 | グーグルとアマゾンの競争 |
|---|
| 1-13 | アップルの価格戦略 |
|---|
| 1-14 | 鶏が先か、卵が先か |
|---|
| 1-15 | 「無邪気に信じて」いるかは関係ない |
|---|
| 第二章 | ソーシャルメディア |
|---|
| 2-1 | ウィキリークスのプラットフォーム化 |
|---|
| 2-2 | Live Nationのプラットフォーム化 |
|---|
| 2-3 | アメリカは実名志向か |
|---|
| 2-4 | オンラインでの数字コラボレーション |
|---|
| 2-5 | 日本でFacebookは生まれない |
|---|
| 2-6 | アメリカのTwitter利用状況 |
|---|
| 2-7 | どうやって毎日ブログを更新するか |
|---|
| 2-8 | Facebookで地図を色分け |
|---|
| 2-9 | Twitterでは「つぶやく」な |
|---|
| 2-10 | データ匿名化の落とし穴 |
|---|
| 2-11 | ソーシャルメディアを使った予測 |
|---|
| 2-12 | ウェブでの匿名性 |
|---|
| 2-13 | Google Waveの開発中止のポイント |
|---|
| 2-14 | Twitterへ斬り込むFacebook |
|---|
| 2-15 | IDをめぐる争い |
|---|
| 2-16 | Facebookの携帯進出 |
|---|
| 2-17 | 絵で見るコミュニケーション手段の拡大 |
|---|
| 2-18 | Facebookとリクナビ |
|---|
| 第三章 | 新聞・放送・出版 |
|---|
| 3-1 | 半世紀に渡る新聞社の収入の推移 |
|---|
| 3-2 | 新聞の価格変動 |
|---|
| 3-3 | ペイウォールはうまくいかない |
|---|
| 3-4 | スポーツ面は必要? |
|---|
| 3-5 | 価格戦争入門 |
|---|
| 3-6 | 誰がオンラインニュースにお金を払うか |
|---|
| 3-7 | 電子出版は誰に必要か |
|---|
| 3-8 | なぜ雑誌は新聞よりうまくいくか |
|---|
| 3-9 | ストライサンド効果 |
|---|
| 3-10 | タブレットと新聞業界とグーグル |
|---|
| 3-11 | NYTのiPad版はいくらにすべきか |
|---|
| 3-12 | グーグルブックスの課題 |
|---|
| 3-13 | 新聞を取らない理由 |
|---|
| 3-14 | 欧州新聞社のオンライン戦略 |
|---|
| 3-15 | ニュースは儲からない |
|---|
| 3-16 | ジャーナリストに必要なスキル |
|---|
| 3-17 | フランスでは新聞が瀕死 |
|---|
| 3-18 | アマゾンのユーザー参加 |
|---|
| 第四章 | 日本・教育・日米比較 |
|---|
| 4-1 | Netflixのスーパースター主義 |
|---|
| 4-2 | TOEFLの行方 |
|---|
| 4-3 | マンガ輸出振興はやめよう |
|---|
| 4-4 | ガラパゴス携帯市場 |
|---|
| 4-5 | 読む量は増えている |
|---|
| 4-6 | 衰退産業が持ち出す文化議論 |
|---|
| 4-7 | アメリカの就活 |
|---|
| 4-8 | ネット選挙 |
|---|
| 4-9 | アメリカの携帯市場 |
|---|
| 4-10 | ワンマンアカデミー |
|---|
| 4-11 | 電子教科書は人格を歪めない |
|---|
| 4-12 | グル―ポンの満足度 |
|---|
| 4-13 | 無償投稿カルチャー? |
|---|
| 4-14 | 災害とガバナンス |
|---|
| 4-15 | 原発の隠れたリスク |
|---|
| 4-16 | 電力市場の自由化 |
|---|
| 4-17 | 京都議定書と震災 |
|---|
|
Training Information
おすすめ企業研修




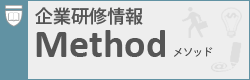
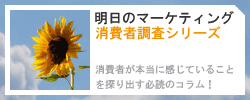
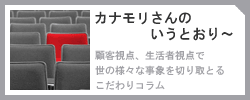
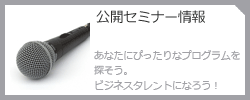
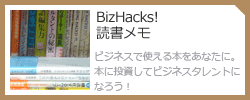
![[読書メモ]世界を制した20のメディア [読書メモ]世界を制した20のメディア](/images/banner/09040301.gif)
![[読書メモ]スパークする思考 [読書メモ]スパークする思考](/images/banner/09040801.gif)