知識デザイン企業

知識デザイン企業
著者:紺野 登
出版社:日本経済新聞出版社
出版日:2008/02

内容紹介
『知識デザイン企業』
iPodの裏はなぜきれいに磨かれているのか?その答えにこれからの経営のヒントが隠されている。常にイノベーションを起こせる驚異の企業モデル「アート・カンパニー」の全貌。
品質追求の経営から「知識デザイン」を中心にした創造的な経営へ――いま、企業のあり方が根本から問われている。21世紀の企業モデルである「アート・カンパニー」とは何か? 豊富な企業事例をもとに解き明かす。
目次
| 第1章 | 創造経済とアート・カンパニーの台頭 |
|---|
| 1 | 創造的サイクルへの大転換 |
|---|
| □ | クオリティ・ムーブメントからクリエイティブ・ムーブメントへ |
|---|
| □ | 「最高文化責任者」と「幸せ度調査」 |
|---|
| □ | 創造経済の3つの側面 |
|---|
| □ | 分析パラダイムはなぜうまく機能しないのか |
|---|
| 2 | 創造経営の旗手たち |
|---|
| □ | スティーブ・ジョブズとアップル |
|---|
| □ | ハワード・シュルツとスターバックス |
|---|
| □ | ベンチャーで・デザイナー、ダイソン |
|---|
| □ | リチャード・ブランソンとヴァージン・グループ |
|---|
| □ | カンペールのロレンツォ・フルーシャ |
|---|
| □ | ラーズ・コリンとオーティコン |
|---|
| □ | 創造経営の先頭集団に共通する「デザイン」とは |
|---|
| 3 | 理念型としてのアート・カンパニーの出現 |
|---|
| □ | 創造経済の世紀の新しい企業モデル |
|---|
| □ | ナレッジ・ワーカーの時代 |
|---|
| □ | 多幸なグローバリゼーションの終焉 |
|---|
| □ | 知識経済は創造パラダイムを志向している、もはや元には戻らない |
|---|
| □ | 経営の新たな基準を求めて |
|---|
| 第2章 | 「モノ<プロダクト>」の概念が変化した |
|---|
| 1 | モノづくりの「モノ」とは何か |
|---|
| □ | 日本のモノづくりが抱える痛みはどこからくるのか |
|---|
| □ | iPodの裏はなぜ鏡のように磨かれていたのか? |
|---|
| □ | ハード、ソフト、サービスのトライアングル結合 |
|---|
| [NOTE] iPodのできるまで |
|---|
| □ | 産業分類思考が創造性を遮断している |
|---|
| 2 | 「モノ<プロダクト>」の概念を変える3つの軸 |
|---|
| □ | 新たなモノ(タンジブル)の意義・復権 |
|---|
| □ | 新たな製品軸1「時間」―ライフサイクル、時間に沿って完成するプロダクト |
|---|
| □ | 新たな製品軸2「感情」―感情的資質、脱・機能主義 |
|---|
| □ | 新たな製品軸3「社会」―社会・環境的ビジネスモデル |
|---|
| 環境の経済性を製品に~環境=負担という公式からの脱却/動き出す超巨大市場BOP(ボトム・オブ・ザ・ピラミッド)/ニュー「ギフトエコノミー」 |
|---|
| 3 | 総合力としてのデザイン |
|---|
| □ | 新たなデザインの役割 |
|---|
| □ | 日本企業の知を解放するデザイン |
|---|
| 第3章 | 「真摯さ」という資産 |
|---|
| 1 | 品質経営の限界と創造経営への進化 |
|---|
| □ | 技術企業から品質企業へ、そして創造企業へ |
|---|
| □ | 品質経営のジレンマ |
|---|
| □ | 真摯なアート・カンパニー |
|---|
| □ | シェア、売上、利益だけの競争にどのような意味があるのかを問うとき |
|---|
| 2 | 企業の資産としての「真摯さ」 |
|---|
| □ | 経営における真摯さ・知の質が問われる経営者 |
|---|
| □ | 「エコエティカ」 |
|---|
| [NOTE]本田宗一郎が引退を決意した瞬間 |
|---|
| 3 | 知識創造パラダイム・モデルへの転換 |
|---|
| □ | ネットワークされた「個」の組織 |
|---|
| □ | 天才とひきこもりとナレッジ・ワーカー |
|---|
| □ | 新しい「プロフェッショナル」 |
|---|
| 4 | 真摯さから生み出されるイノベーション |
|---|
| □ | 何のためのイノベーションか? |
|---|
| □ | 真摯さの経営 |
|---|
| ディスコ/エーザイ/新明和工業 |
|---|
| □ | 真摯なアート・カンパニーに求められる知 |
|---|
| 第4章 | 知識デザイン:知をオーガナイズする |
|---|
| 1 | アート・カンパニーのためのデザイン |
|---|
| □ | 創造経営の方法論として「デザイン」を提起する |
|---|
| □ | グッドデザイン大賞と痛くない注射針 |
|---|
| 2 | 「無名の質」を生み出す |
|---|
| □ | 何をデザインするのか? |
|---|
| □ | 「無名の質」の7つの特性 |
|---|
| □ | 工業デザインから知識デザインへ |
|---|
| □ | 知識デザインのプロセスが求められる |
|---|
|
| 3 | 経営とデザインはどのように関わってきたか |
|---|
| □ | 歴史的経緯を振り返る |
|---|
| 経営とデザインの歴史的経緯(19世紀から21世紀へ) |
|---|
| □ | 「新たな知の普及」としてのイノベーション |
|---|
| 4 | 価値を生み出すトータル・プロセスとしてのデザイン |
|---|
| □ | 多様な知をまとめ上げる、が価値を生む |
|---|
| □ | タコツボ化を超える知識デザイン |
|---|
| □ | 見えないものを見る、創ること |
|---|
| □ | ないものを生み出す力はどこから生まれるか |
|---|
| □ | デザイン・リーダーシップの役割 |
|---|
| 5 | 変化するデザイン・サービス |
|---|
| □ | 日本のモノづくりに欠けているもの |
|---|
| DEGW/ゲンスラー |
|---|
| [NOTE]PSFに学ぶ知識サービス組織 |
|---|
| □ | デザインしないデザイナー |
|---|
| 第5章 | 知識デザインの「方法論」 |
|---|
| □ | 知識デザインを構成する要素 |
|---|
| 1 | 知識デザインに必須な2つの軸「体験的認知」と「内省的認知」 |
|---|
| 2 | 体験的認知を起点とする「経験デザイン」 |
|---|
| 3 | 体験的認知によるデザインに内省的認知を織り込むにはどうするか |
|---|
| 知識デザインとデザイン・エンジニアリング/アップルのデザイン |
|---|
| 4 | 知識デザインの構図 |
|---|
| 知識デザイン=知識創造×デザイン/重要になるリサーチとしてのデザイン |
|---|
| 5 | 環境・文化的要素をデザインに取り込む |
|---|
| 6 | 綜合する言語「パタン・ランゲージ」 |
|---|
| 無名の質を生み出すための共通言語/パタン・ランゲージによるデザインの実際/背後の要因(動員)がパタンを結びつける |
|---|
| [NOTE]言語の本質は創造 |
|---|
| 7 | 知識デザインは人間知の総動員 |
|---|
| 補論 | 知識デザインの実践:コンセプト・デザインにおける応用 |
|---|
| 1 | 前提:知のディシプリンの要請 |
|---|
| 2 | 知の方法論の綜合としての知識創造モデル |
|---|
| 3 | 知識創造の背後にある哲学・科学 |
|---|
| 4 | 「コンセプト・デザイン」への知の方法論の展開 |
|---|
| 5 | グラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA) |
|---|
| 6 | アブダクション・エンジン |
|---|
| 7 | 本質的に見えないものを見えるようにする |
|---|
| 第6章 | アート・カンパニーの条件 |
|---|
| 1 | 本当に望まれるもの |
|---|
| □ | 新たな消費者意識の台頭 |
|---|
| □ | 企業に求められる審美性 |
|---|
| □ | 社会と環境と人間のつながりが究極の課題に |
|---|
| 2 | 新たな知識都市経済の時代 |
|---|
| □ | 忘れていた資本、エコキャピタル |
|---|
| □ | ナレッジ・シティ |
|---|
| □ | 都市の知的集積がアート・カンパニーを生む |
|---|
| □ | マイクロ・ファームの台頭 |
|---|
| 3 | 組織の知的集積の質がイノベーションを駆動する |
|---|
| □ | 革新を生み出すための知の集結 |
|---|
| □ | フューチャーセンター:組織の知識資産を駆動するハブ |
|---|
| □ | 知の伝統を重視する |
|---|
| □ | 伝統からのイノベーション |
|---|
| [NOTE]資生堂:日本の伝統的アートカンパニー |
|---|
| 4 | アート・カンパニー実践のための思想―可能主義的実践(Practice on Possibilism) |
|---|
| □ | 組織のセンスメーキング能力 |
|---|
| □ | 可能主義の経営 |
|---|
| 5 | アート・カンパニーの10の条件 |
|---|
| |
|---|
| あとがき |
|---|
| 主要参考文献 |
|---|
|
Training Information
おすすめ企業研修




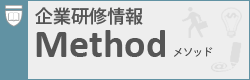
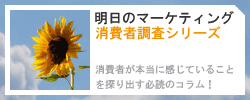
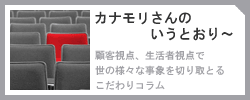
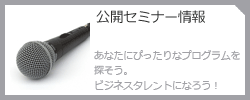
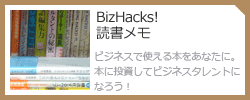
![[読書メモ]世界を制した20のメディア [読書メモ]世界を制した20のメディア](/images/banner/09040301.gif)
![[読書メモ]スパークする思考 [読書メモ]スパークする思考](/images/banner/09040801.gif)