TOP » 読書メモ » プラットフォーム ブランディング
プラットフォーム ブランディング

プラットフォーム ブランディング
著者:川上 慎市郎/山口 義宏
出版社:ソフトバンククリエイティブ
出版日:2013/3/30
Amazon商品の説明より
『プラットフォーム ブランディング』
世界で勝てるブランドをいかにしてつくるのか
アップルをはじめ、強大なブランドとなった企業がグローバル市場を席巻する一方、韓国や中国の新興ブランドにさえ敗北を喫し、苦戦を強いられる日本企業。
かつて「モノづくり大国」といわれたこの国は何をどこで間違えたのか?
グローバルで戦える強いブランドをつくるにはどうしたら良いか?
eコマースやソーシャルネットワークなどのビジネスが世界中で隆盛を極めているが、「プラットフォーム」の活用という考え方そのものは、製造業をはじめ、より広範囲で応用可能なものだ。
とりわけブランドそのものを「共創のプラットフォーム」として再定義することは、あらゆる製品がコモディティ(汎用品)化する時代に儲かるビジネスをつくり出す上で、欠かすことができない。
かつての成功体験に縛られる日本企業を「次」のステージに導くために必要なアイデアとは何か?
顧客の心の中にそのブランドが提供する良い体験の知覚認識を形成し、市場競争力を高めるためにどんな戦略が必要か?
ビジネス誌記者を経て現在はビジネススクールでマーケティング領域の教員を務める川上と、ブランド戦略を専門とするコンサルタントの山口が次世代のブランドのつくり方を語る!
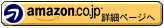
目次
| まえがき |
|---|
| 序章 | 日本企業はなぜ負け続けるのか? ─ブランド戦略の「不在」と「失敗」 |
|---|
| モノづくり大国の「崩壊」 |
|---|
| 「強いブランド」が足枷になるとき |
|---|
| 電機業界の凋落から何を学ぶべきなのか? |
|---|
| 「顧客の体験」を載せるプラットフォーム |
|---|
| 第一章 | 知らないと恥ずかしいブランディング基礎の基礎 |
|---|
| サイエンスとしてのブランド戦略 |
|---|
| ブランドに対する三つの誤解 |
|---|
| 「識別記号」と「知覚価値」 |
|---|
| ブランド成立への三つのステップ |
|---|
| ブランドは選択判断のコストを下げる |
|---|
| ポイントは「体験の一貫性」 |
|---|
| 変えることと変えないことのバランス |
|---|
| ブランド崩壊への誘惑 |
|---|
| ブランド育成とビジネス成長を両立させる舵取り |
|---|
| ブランド知覚価値を重視するメリット/デメリット |
|---|
| ブランド戦略の二類型 |
|---|
| 第二章 | 「体験」が最高のブランドをつくる |
|---|
| アップルとフォルクスワーゲンはなぜ高くても世界中で売れるのか? |
|---|
| グローバル化は「センスのよさ」を求める |
|---|
| 「モノ」から「体験」への価値転換 |
|---|
| アップルが経験した二つのイノベーション |
|---|
| 新たな体験フローの設計 |
|---|
| 「まだないもの」の価値を明確にするには? |
|---|
| 生活者を巻き込むブランディング |
|---|
| 共創された「勝間和代」というブランド |
|---|
| ブランドは「場(プラットフォーム)」という発想 |
|---|
| 第三章 | 体験価値を共創するプラットフォーム |
|---|
| 「プラットフォーム」とは何か? |
|---|
| 「オープン・プラットフォーム」の登場 |
|---|
| プラットフォームの機能 |
|---|
| ①コミュニケーションを低コストで媒介する |
|---|
| ②相互ネットワーク効果で売り手と買い手双方に価値を創出 |
|---|
| プラットフォームが顧客を呼び込む |
|---|
| プラットフォーム化のリスク |
|---|
| プラットフォームは一日にしてならず |
|---|
| プラットフォーム構築への四つのプロセス |
|---|
| ①価値提供すべき生活者の「大きな欠損」を発見する |
|---|
| ②提供する体験の価値を絞り込み、最大化する |
|---|
| ③体験フロー全体の価値を高めるパートナーを引き込む |
|---|
| ④周辺領域へプラットフォームを拡大する |
|---|
| フェイスブックのジレンマ―体験価値に貢献しないプラットフォームの不毛 |
|---|
| 第四章 | 進化するブランド戦略 |
|---|
| 体験価値で売るということ |
|---|
| 生活者主語のブランドへ |
|---|
| ブランドが生活者を支援するという発想 |
|---|
| レバレッジ効果を高めるための選択 |
|---|
| レバレッジ視点① 商品群の横串となる共通要素に集中投資 |
|---|
| レバレッジ視点② 「メディア化」する商品に集中投資 |
|---|
| レバレッジ視点③ 関連商品の購買につながる商品に集中投資 |
|---|
| 日本のブランドがレバレッジの利いた戦略を苦手とする理由 |
|---|
| ブランドの未来は誰が決めるのか? |
|---|
| 経営視点から見たブランド戦略の位置付け |
|---|
| ブランド軸の経営とは何か? |
|---|
| 欠かせないトップの支援と権限の委譲 |
|---|
| ブランドが強い企業とブランド戦略に強い企業は違う―カリスマ&技術依存から脱却せよ |
|---|
| ブランド戦略のミスは組織の慣性が誘発する |
|---|
| 第五章 | 顧客体験価値デザインとブランド戦略の実践 |
|---|
| ブランド戦略実践への五つのフェーズ |
|---|
| フェーズ1 プロジェクト体制と戦略方向性検討 |
|---|
| フェーズ2 ブランドターゲットの設定 |
|---|
| フェーズ3 インサイトに基づく顧客体験デザイン |
|---|
| フェーズ4 ブランド戦略と4P施策要件の策定 |
|---|
| フェーズ5 PDCAサイクルの設計と運用 |
|---|
| 終章 | 日本企業はまた勝てるか?─「理念」から「スキル」へ |
|---|
| 日本企業がブランドに取り組んできた歴史 |
|---|
| 二〇〇〇年代前半に顧客体験価値の最大化を目指した先進企業ソニー |
|---|
| ブランド戦略の実行にはシンプルな組織力学が重要となる |
|---|
| 電機業界はあなたの会社の一〇年後を映す鏡 |
|---|
| ポストカリスマ創業者時代のサバイバルレース |
|---|
| あとがき |
|---|
|
|---|
|
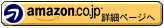
Training Information
おすすめ企業研修


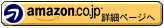

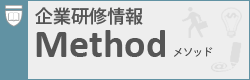
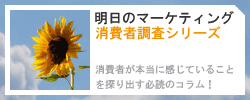
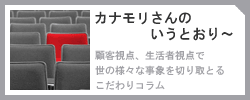
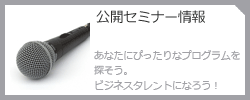
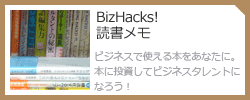
![[読書メモ]世界を制した20のメディア [読書メモ]世界を制した20のメディア](/images/banner/09040301.gif)
![[読書メモ]スパークする思考 [読書メモ]スパークする思考](/images/banner/09040801.gif)